税理士事務所との契約を解消し、自力での会計処理を決意。
顧問料の負担に対しミスが多く、いっそ自分でやろう!
と決めたものの、すぐに壁にぶち当たりました。自力経理の最大の試練は、決算期をまたぐ処理です。
今回は、私たちのような初心者が必ず遭遇する「費用計上漏れ」、特に「期ずれ」の解決策を、私たちの実例(税理士報酬の未払計上漏れ)をもとに、その影響も含めて徹底的に解説します。
😱発生!「前期の費用」を「当期に支払った」問題
当社の決算は9月締めで、税理士報酬(顧問料と決算料合計\213,400)は決算確定後の11月に支払う流れでした。
本来、21期末に「未払金」として計上すべきこの費用の計上が、最終的に依頼していた税理士事務所によって漏れていたことが判明。
迎えた22期11月に予定通り支払いを行ったものの、「21期の費用」を「22期に支払った」この処理をどうすればいいか困っています。
【期ずれの深刻な影響】
この計上漏れを放置すると、単に仕訳に困るだけでなく、以下のような深刻な影響が出ます。
-
21期(前期)の利益が過大になる: 本来計上すべき費用(\213,400)が計上されなかったため、帳簿上の利益がその分増えてしまいます。その結果、法人税や地方税を本来よりも多く支払っていた可能性があります。
-
22期(当期)の利益が過小になる: 当期に支払った際、誤って全額を「支払手数料」として計上してしまうと、当期の費用ではない過去の費用が当期の利益を押し下げてしまいます。これでは、今の期の経営成績が正しく把握できなくなります。
正しい会社の状況を把握し、税金を適正に納めるためにも、この期ずれは必ず修正しなければなりません。
初心者向け解説:なぜ「未払金」が必要なのか?(発生主義と勘定科目)
この問題の鍵は、会計の超重要ルール「発生主義」にあります。
現金主義がお金の出金ベースで記録するのに対し、発生主義は「サービスを受けた(費用が発生した)時点」で費用を記録します。
|
会計ルール |
費用を計上するタイミング |
|---|---|
|
発生主義 |
サービスを受けた日(=決算日) |
|
現金主義 |
お金を支払った日(=11月) |
税理士の決算サービスは「21期末」に完了しています。したがって、21期末の帳簿に費用と負債を計上する義務がありました。
勘定科目も使い分けよう!「未払金」と「未払費用」
自力経理に挑戦するなら、この違いも把握しておくと、より正確な処理ができます。
|
勘定科目 |
定義(使い分け) |
当社の事例での適用 |
|---|---|---|
|
未払金 |
本業ではない、単発的な取引で生じた未払い債務。(備品購入のツケ、固定資産の未払いなど) |
使用可。税理士報酬を単発の取引とみなせば使えます。 |
|
未払費用 |
継続的なサービスの提供に対して、まだ支払いが済んでいない債務。(家賃、保険料、顧問料、利息など) |
より正確。税理士の顧問契約は継続的なサービスであるため、こちらが推奨されることも多いです。 |
今回は既に「未払金」という言葉を使ってしまいましたが、継続的な顧問サービスであれば「未払費用」を使う方が、厳密な会計処理としては望ましいことを覚えておきましょう。
✅解決策の救世主:「前期損益修正損」
既に21期の申告が完了している場合、前期の決算書を修正するのは非常に手間がかかります。
そこで、当期(22期)で過去のミスを処理するために「前期損益修正損」を使用します。
「前期損益修正損」とは?
これは、過去の年度の会計処理のミスや漏れを、当期の決算でまとめて修正するための特別な費用勘定(特別損失)です。
税務上も、過去の経費として正しく処理できることが一般的です。
🌟 実際の仕訳(22期11月)と税金の考慮
支払いを計上する際、税理士報酬は源泉所得税の対象であり、消費税の課税対象でもあります。
ここでは源泉徴収(\10,000と仮定)と消費税(\19,400と仮定)を考慮した仕訳例を提示します。
(※報酬総額\213,400の内訳は、税抜報酬\185,000 + 消費税\19,400 + 源泉税\9,000と仮定し、便宜上の金額を使用しています。実際の請求書をご確認ください。)
|
日付 |
借方勘定科目 |
借方金額 |
貸方勘定科目 |
貸方金額 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
22期 11月 |
前期損益修正損 (報酬) |
\185,000 |
普通預金 |
\213,400 |
21期税理士報酬(本体)の計上漏れを修正 |
|
|
仮払消費税 (消費税) |
\19,400 |
預り金 (源泉所得税) |
\9,000 |
21期税理士費用源泉税・消費税処理 |
|
|
(差額調整) |
\9,000 |
|
|
(預り金と前期損益修正損の差額調整) |
ワンポイント! 支払いの内訳を請求書で確認し、本体価格(前期損益修正損)、消費税(仮払消費税)、そして天引きした源泉所得税(預り金)の3つに分けて処理することが、自力経理において正確性を高めるために必須です。源泉所得税は、翌月10日までに税務署に納付する義務が発生します。
源泉所得税をまるめて簡易的な仕分けは次のようになります。
実際に22期11月に税理士事務所へ¥213,400を支払った際の仕訳です。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 前期損益修正損 | ¥213,400 | 普通預金(または現金) | ¥213,400 | 21期末計上漏れの税理士顧問料等支払い |
-
前期損益修正損: 過去の会計期間の損益を修正するために当期に計上する特別な勘定科目です。これは特別損失として計上されます。
-
普通預金: 実際に支払った金額だけ預金が減少します。
振込に係った手数料はこの仕訳とは別になります。振込を行った時点での単純な経費として処理します。
|
支払手数料 (振込手数料) |
¥55 |
|
|
振込手数料(当期費用)の計上 |
👩💻 自力経理へのアドバイス:次の決算に向けて(恒久対策)
今回の件で、自力経理の難しさを痛感したかもしれません。
しかし、今回の教訓を活かせば、費用計上漏れを防ぐための強固な体制を構築できます。
次の決算(9月30日)で必ずやることリスト
-
「未払金・未払費用」の洗い出しの徹底: 決算日(9月30日)時点で、まだ請求書が届いていなくても、その月でサービスを受けた費用を全てリストアップしましょう。特に、毎月発生するが支払いが翌月になる費用(家賃、公共料金、サブスクリプションサービスなど)は要注意です。
-
適切な勘定科目の選択と統一: 継続的な未払いは「未払費用」、単発の未払いは「未払金」と、自社ルールを決めて統一します。曖昧な処理をなくすことが、ミスの予防につながります。
-
仕訳の実行と確認: 必ず決算日(9月30日)付で「費用 / 未払金(未払費用)」の仕訳を計上し、決算書に負債として反映されているかを必ず確認しましょう。
-
内部の証憑(しょうひょう)管理の強化: 計上漏れを防ぐため、請求書や契約書が届いたらすぐに経理担当者に連携するルールを徹底しましょう。特に、決算月前後の取引については、請求書が届いていなくてもサービス提供の完了を示す証拠(検収書など)を保管することが重要です。
私の所は、WEBマディア会社で、商品や物の動きはほぼありません。ネット系のビジネスの会社では、自力での決算、納税は十分可能です。
金額の多寡ではなく、仕分けするものがそんなにございません。今回、税理士事務所から脱却していろいろと勉強になりました。
自力経理はそれなりに大変なところもありますが、会社のお金の流れを完全に把握し、経営判断に活かせる最高のチャンスです。
一つずつ知識を増やし、乗り越えていきましょう!
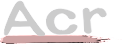



コメント