Webサイト運営やアプリ開発でGoogleアドセンス(Google AdSense)を導入する企業や個人事業主の方が多くみえます。
しかし、その収益は通常の国内取引とは異なる点が多々あり、会計処理(仕訳)に迷うケースが少なくありません。
特に、以下の3つのポイントが経理処理を複雑にします。
-
国外取引であること(消費税の扱いは?)
-
支払い基準額(8,000円)があり、毎月入金されるとは限らないこと
-
「無効なトラフィック」調整で、確定額と入金額がズレること
これらの特徴を踏まえた上で、社内マニュアルとして運用している2パターンの仕訳方法を、用語解説付きで徹底解説します。
会計の基本原則に忠実な「厳格法」と、実務上の手間を削減する「簡便法」。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に最適なルールを構築する一助となれば幸いです。
1. 最初に確認:アドセンス収益と消費税
まず、最も重要な消費税の扱いです。
Googleアドセンスの収益は、Googleの国外法人(例:Google Asia Pacific Pte. Ltd.)との取引であり、国外の事業者に対して行う広告配信という「役務の提供」にあたります。
これは日本の消費税法上「国外取引」とみなされ、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。
※ 「不課税」と「免税」「非課税」の違い(重要)
ここで、「不課税」は「免税」(輸出取引など)とは異なる点を理解しておく必要があります。
-
不課税取引(アドセンス収益など): そもそも消費税の土俵(課税対象)に乗らない取引。消費税の納税額計算において、「課税売上高」にも「分母の総売上高」にも含まれません。
-
免税取引(輸出など): 課税対象だが、政策的に税率0%が適用される取引。「課税売上高」としてカウントされます。
-
非課税取引(土地の売買、家賃など): 課税対象だが、社会政策的配慮から課税しない取引。「課税売上高」には含まれませんが、「分母の総売上高」には含まれます。
アドセンス収益が「不課税」であることは、国内の課税売上と非課税売上が混在する事業者にとって、「課税売上割合」の計算に影響を与えないという点で重要です。
結論:アドセンス収益の仕訳の際は、消費税を考慮する必要はありません。 (会計ソフトの税区分は「対象外」や「不課税」を選択し、摘要欄に「不課税」とメモしておくと分かりやすいです)
送金者であるGoogieの名義はどこの国からなのか?
Googleアドセンスの収益の送金元は、利用者の所在地によって異なりますが、日本では主に「Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール法人)」または「Google Ireland Limited(アイルランド法人)」から送金されます。
送金元の国が複数存在するのは、Googleが地域ごとに異なる法人を設立しているためです。
日本の消費税との関係
Googleアドセンスの収益は、日本の消費税とは関係ありません。
これは、国外の事業者から役務の提供を受けている「国外取引」と見なされるためです。
具体的な税務上の取り扱いは以下の通りです。
受け取る収益について
Googleアドセンスの収益は、国外の事業者(Google Asia Pacific Pte. Ltd.など)からの支払いであるため、日本の消費税法上は「不課税」取引となります。
日本の消費税の課税対象ではないため、収益に消費税は加算されません。
あなたが課税事業者であっても、この収益に対して消費税を納める必要はありません。
広告の出稿者は?経費として支払うGoogle広告の費用について
AdSense収益とは異なり、日本国内の事業者がGoogle広告を出稿する際にGoogleに支払う費用は、2019年4月1日より消費税の課税対象になりました。
これは、サービス提供者が日本の法人であるグーグル合同会社になったためです。
ただし、AdSenseの収益は消費税の対象外である一方、個人の所得として所得税や住民税の課税対象にはなります。
年間の所得が一定額を超えた場合は確定申告が必要です。
2. 仕訳の基本(用語解説)
次に、仕訳を理解するために最低限必要な会計用語をおさらいします。
|
用語 |
意味 |
|---|---|
|
発生主義 |
お金が動いた時点(入金時)ではなく、収益や費用が経済的に発生・確定した時点で計上する会計ルール。企業の正しい「期間損益計算(その期間にいくら稼ぎ、いくら使ったか)」を行うための大原則です。 |
|
現金主義 |
実際にお金が入金・出金した時点で収益・費用を計上するルール。簡易的な方法ですが、法人税の申告などでは原則として認められません。 |
|
売上(うりあげ) |
会社の本業で得た収益。アドセンス収益もこれにあたります。(勘定科目は「売上」のほか「雑収入」などを使う場合もありますが、継続して使用することが重要です) |
|
売掛金(うりかけきん) |
収益は確定したが、まだ入金されていない「お金をもらう権利」。会社の「資産」の一種です。 |
|
普通預金 |
銀行口座のお金。「資産」の一種です。 |
|
雑損失(ざつそんしつ) |
営業活動以外で発生した、少額で重要性の低い損失・費用です。「無効なトラフィック調整額」など、他の勘定科目に当てはめにくい差額処理に使われます。 |
|
期間損益計算 |
特定の期間(例:1ヶ月や1年間)の経営成績を明らかにするため、その期間に属する収益と費用を対応させて利益を計算すること。発生主義の主な目的です。 |
アドセンスの仕訳が複雑なのは、この「発生主義」をいつの時点と捉えるか(=収益がいつ確定したか)について、複数の解釈ができてしまうためです。
3. 【パターンA:厳格法】毎月の発生主義に基づく仕訳
<こんな会社向け>
-
月ごとの業績(損益)を1円単位で正確に把握したい。
-
会計監査や税務調査に対し、厳密な発生主義(期間損益計算)で説明したい。
-
個人事業主で、青色申告(65万円控除)の要件である「複式簿記」を遵守したい。
この方法は、Googleが「収益が確定した」と通知した時点(通常、翌月3日頃)で、金額の大小にかかわらず(8,000円未満でも)毎月売上を計上する、会計原則に最も忠実な方法です。
ステップA-1:収益の確定(毎月・全額計上)
たとえ支払い基準額(8,000円)未満で入金がなくても、管理画面で収益が確定したら、その金額を「売掛金」として計上します。
これにより、「1月に発生した収益は、1月の売上」として正しく計上されます。
【例】1月 3,000円、2月 3,000円、3月 3,000円が確定した場合
|
日付 |
勘定科目(借方) |
金額 |
勘定科目(貸方) |
金額 |
摘要(不課税) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1月末日 |
売掛金 |
3,000 |
売上 |
3,000 |
Adsense報酬確定分(1月分) |
|
2月末日 |
売掛金 |
3,000 |
売上 |
3,000 |
Adsense報酬確定分(2月分) |
|
3月末日 |
売掛金 |
3,000 |
売上 |
3,000 |
Adsense報酬確定分(3月分) |
-
根拠資料(重要): この時点では「支払い領収書」は発行されません。税務調査などで根拠を問われた場合、Googleアドセンス管理画面の「お支払い情報」 ⇒「取引履歴」で、収益が確定し残高に加算された画面が唯一の証憑(しょうひょう)となります。 必ず日付と金額が明確にわかる画面をPDFやスクリーンショットで保存し、「20240131_3000_Adsense収益確定.pdf」のようにファイリングしましょう。
-
帳簿の状態: 3月末時点で、帳簿には「売掛金 9,000円」「売上 9,000円」が計上されます。貸借対照表(B/S)には資産として売掛金9,000円が残り、損益計算書(P/L)には各月に3,000円ずつの売上が計上されます。
ステップA-2:入金時の処理(無効トラフィック調整あり)
4月に入金される際、無効なトラフィックの審査により過去の収益が調整され、500円が引かれ、8,500円しか入金されなかった場合の仕訳です。
-
帳簿上の売掛金: 9,000円
-
実際の入金額: 8,500円
-
差額(損失): 500円
|
日付 |
勘定科目(借方) |
金額 |
勘定科目(貸方) |
金額 |
摘要(不課税) |
|---|---|---|---|---|---|
|
4月入金日 |
普通預金 |
8,500 |
売掛金 |
9,000 |
Googleアドセンス1-3月分入金 |
|
|
雑損失 |
500 |
|
|
無効トラフィック調整による減額 |
-
ポイント: 売掛金は過去に計上した全額(9,000円)を貸方に計上し、消し込みます(債権の消滅)。そして、実際の入金額(8,500円)との差額を「雑損失」として借方に費用計上します。 この「雑損失」は、過去の売上に対する「値引き」とも解釈できますが、どの月の売上に対する調整か特定が困難なため、実務上は入金時の損失として処理するのが最も効率的です。
-
根拠資料: 発行された「支払い領収書」や、調整額(無効なトラフィック)が記載された「取引履歴」画面を保存します。
4. 【パターンB:実務優先法】入金確定額に基づく簡便な仕訳
<こんな会社向け>
-
経理の仕訳をできるだけシンプルにしたい。
-
月次の細かい業績のズレは許容し、年間の損益が合っていれば良い。
-
「雑損失」などの調整仕訳をなくし、売掛金の残高管理を容易にしたい。
この方法は、「無効なトラフィック調整」が完了した「最終的な振込金額」こそが、その期間に計上すべき真の売上である、と捉える実務的な方法です。
発生主義の「収益確定時点」を、「Googleによる調整が完了し、支払いが実行された時点」と解釈する方法です。
ステップB-1:収益の確定(入金が確定した月のみ)
入金が発生しない月(8,000円未満の月)は、あえて仕訳を行いません。
そして、複数月分の収益が合算され、調整後の振込額が確定した月に、その金額を一括で売上計上します。
【例】1月~3月分が合算され、4月に調整後8,500円の入金が確定した場合
-
1月末、2月末:仕訳なし (この時点では、月次の損益計算書にアドセンス収益は0円と表示されます)
-
3月末(入金が確定した月の前月末):ここで初めて売上を計上します。
|
日付 |
勘定科目(借方) |
金額 |
勘定科目(貸方) |
金額 |
摘要(不課税) |
|---|---|---|---|---|---|
|
3月末日 |
売掛金 |
8,500 |
売上 |
8,500 |
Adsense報酬確定分(1-3月分・調整済) |
-
ポイント: 1月、2月の売上は計上されず、すべて3月の売上として計上されます。これにより、月ごとの業績は不正確になりますが、四半期や年単位での合計額は正しくなります。計上する金額は実際の入金額(8,500円)を使います。
-
根拠資料: 発行された「支払い領収書」または、入金が確定した「取引履歴」画面。調整後の最終金額が根拠となります。振込日の自動支払いの青いクリック文字先から根拠資料が入手できます。
ステップB-2:入金時の処理
ステップB-1で計上した売掛金(8,500円)と、実際に入金される金額(8,500円)が完全に一致するため、仕訳は非常にシンプルです。
|
日付 |
勘定科目(借方) |
金額 |
勘定科目(貸方) |
金額 |
摘要(不課税) |
|---|---|---|---|---|---|
|
4月入金日 |
普通預金 |
8,500 |
売掛金 |
8,500 |
Googleアドセンス1-3月分入金 |
-
ポイント: 「雑損失」の出番はありません。売掛金の残高も0円となり、帳簿がスッキリします。
5. まとめ:どちらの方法を選ぶべきか?
どちらの方法も、会計上「間違い」ではありません。
会社の規模や、経理に割けるリソース、月次決算の重要度によって選択してください。
|
比較 |
パターンA:厳格法 |
パターンB:実務優先法 |
|---|---|---|
|
メリット |
・月ごとの業績が正確 ・会計原則に最も忠実 ・青色申告65万円控除の要件に合致 |
・仕訳が圧倒的にシンプル ・「雑損失」が不要 ・売掛金管理が楽(ズレない) |
|
デメリット |
・仕訳が煩雑(特に調整時) ・「雑損失」の管理が必要 ・領収書がない月の資料保存が必須 |
・月ごとの業績把握は不正確になる (売上が特定の月に集中するため) ・厳密な発生主義とは言えない |
|
推奨 |
・月次決算を重視する法人 ・青色申告(65万円控除)の個人 |
・経理の簡素化を優先する法人・個人 ・アドセンス収益が売上全体に占める割合が低い会社 |
どの方法を選ぶかのヒント
-
法人(株式会社など): 原則はパターンA(厳格法)です。しかし、アドセンス収益の金額が会社全体の売上に対して非常に小さい場合(例:売上全体の1%未満など)、会計の「重要性の原則」に基づき、パターンB(実務優先法)を採用することも税務上許容される可能性が高いです。
-
個人事業主(青色申告65万円控除): 正規の簿記の原則(複式簿記)が求められるため、パターンA(厳格法)を強く推奨します。
-
個人事業主(白色申告・青色10万円控除): 年単位の収支が合っていれば良いため、パターンB(実務優先法)で問題ありません。
忘れずに保存すべき資料(7年保存)
最後に、どちらの方法を採用するにせよ、証憑(しょうひょう)となる資料の保存は義務です。
|
処理 |
保存する資料 |
|---|---|
|
入金がない月 (パターンAのみ) |
Googleアドセンス「お支払い情報」 ⇒ 「取引履歴」画面 (月次収益が確定したことがわかるもの。PDF等で保存) |
|
入金があった月 (パターンA・B共通) |
Googleアドセンス「お支払い」 ⇒「支払い領収書(receipt)」 (調整額の内訳がわかる取引履歴もあれば尚可) |
|
銀行口座 (パターンA・B共通) |
入金履歴がわかる通帳やインターネットバンキングの明細 |
自社の運用に合った方法を選び、「一度決めたルールを継続して適用する」ことが、会計処理において最も重要です。
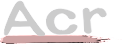



コメント