📌 はじめに:なぜ按分が必要なの?【税務上の要件と処理の原則】
役員のご自宅を事務所として利用している場合、電気や水道などの費用は「仕事(事業活動)」と「私生活(プライベート、家事関連)」の両方で使われています。
会社が経費として計上できるのは、法人税法上、「業務の遂行上必要であった」と合理的に説明できる部分に限られます。
このため、支払総額から仕事に使用した割合を計算し、公私を明確に区別して経費の額を確定させる必要があります。
この合理的な区別を行う計算を家事按分(かじあんぶん)と呼びます。
🏠 今回のルールと1/3の合理性
あなたの会社では、電気料金と水道料金について、以下のルールで按分を行います。
|
項目 |
支払者 |
支払頻度 |
会社の経費とする割合(按分率) |
按分の合理的な根拠 |
|---|---|---|---|---|
|
電気料金 |
役員個人 |
毎月 |
1/3(約33.3%) |
主に業務に使用するスペースの面積比 |
|
水道料金 |
役員個人 |
2ヶ月ごと |
1/3(約33.3%) |
主に業務に使用するスペースの面積比 |
合理的な根拠について深掘り
税務上、按分比率の根拠として最も客観的で認められやすいのは「使用面積の割合」です。
例えば、「自宅全体の床面積100%に対し、事業専用のオフィススペース(仕事部屋)が33%を占めているため、按分率を1/3(約33.3%)とする」といった形で、比率の根拠となる計算書や図面を必ず保管しておきましょう。
また、使用時間の割合でも根拠となります。「1日8時間の仕事時間で按分率を1/3(約33.3%)とする」といった形でもいいでしょう。
🏠 今回のルールと1/3の合理性【時間による按分基準】
今回の経費精算では、以下のルールと「労働時間」に基づく根拠を採用します。
|
項目 |
支払者 |
支払頻度 |
会社の経費とする割合(按分率) |
按分の合理的な根拠 |
|---|---|---|---|---|
|
電気料金 |
役員個人 |
毎月 |
1/3(三分の一) |
1日の総時間(24時間)に対する事業使用時間(8時間)の割合 |
|
水道料金 |
役員個人 |
2ヶ月ごと |
1/3(三分の一) |
1日の総時間(24時間)に対する事業使用時間(8時間)の割合 |
合理的根拠の計算: 税務上、按分比率の根拠として「時間」を用いる場合、以下の計算に基づき1/3を導きます。
事業使用時間÷総時間= 8時間÷24時間= 1/3
この根拠を裏付けるため、次のセクションにあるような「家事按分規定」を文書化し、保管することが必須となります。
📄 家事按分規定(文書例):労働時間(1/3)を根拠とする
以下の文書を正式な社内規定として記録・保管し、按分処理の客観的な根拠としてください。
家事按分に関する規定
(役員自宅兼事務所の光熱費精算基準)
第1条(目的)
本規定は、役員自宅を事務所として使用する場合において、私的費用と事業遂行上の費用を合理的に区分し、適正な経理処理を行うことを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規定は、事業主である役員が個人で支払いを行う水道光熱費(電気料金、水道料金)に適用する。
第3条(家事按分の基準)
水道光熱費の事業使用割合は、以下の計算に基づき定める。
1. 事業活動の総時間: 1日あたりの総時間は24時間とする。
2. 事業に使用する時間: 役員の標準的な労働時間を1日8時間とする。
3. 按分比率の決定:
事業使用時間÷総時間= 8時間÷24時間=1/3
上記に基づき、電気料金及び水道料金の1/3を事業経費とする。
第4条(端数処理)
按分計算により円未満の端数が生じた場合、継続性の観点から切り捨てにより処理するものとする。
付則
本規定は、20XX年X月X日より施行する。
💡 知っておきたい会計用語
経理処理の基礎となる用語を改めて解説します。これらの用語が仕訳(ルール)を形作っています。
|
用語 |
読み方 |
意味と役割 |
補足事項 |
|---|---|---|---|
|
勘定科目 |
かんじょうかもく |
会社の取引内容(お金の出入り)を分類・記録するための見出しです。取引を整理し、財務諸表作成の基礎となります。 |
費用、収益、資産、負債、純資産の5つのグループに分類されます。 |
|
水道光熱費 |
すいどうこうねつひ |
会社が事業のために使用した水道、電気、ガスなどの費用を記録する勘定科目(費用グループ)です。この科目に計上できるのは按分後の金額のみです。 |
暖房器具や給湯器の燃料費なども含みます。 |
|
役員借入金 |
やくいんかりいれきん |
会社が役員から一時的にお金を借りている状態を示す勘定科目(負債グループ)です。今回は役員が会社の経費を立て替えてくれたという事実を記録するために使用します。 |
会社から役員へ資金を貸し付ける場合は役員貸付金となり、逆の処理となります。 |
|
借方 |
かりかた |
仕訳の左側に記載します。「資産の増加」「負債の減少」「費用の発生」のいずれかを示します。 |
ドイツ語で「Soll(ゾル)」とも呼ばれ、「借入」「要求」を意味します。 |
|
貸方 |
かしかた |
仕訳の右側に記載します。「資産の減少」「負債の増加」「収益の発生」のいずれかを示します。 |
ドイツ語で「Haben(ハーベン)」とも呼ばれ、「所有」「ある」を意味します。 |
|
仕訳 |
しわけ |
すべての取引を「借方」と「貸方」の二面から捉え、特定の勘定科目に金額を振り分ける作業(会計処理の基本)です。 |
「取引の二面性」に基づいて行われ、借方と貸方の金額は必ず一致します。 |
📝 経費精算のための仕訳手順(具体的なフロー)
光熱費の精算は以下の3つのステップで処理を行います。
ステップ 1: 役員が個人で支払いをしたとき
役員の口座から光熱費の全額が引き落とされた時点では、会社側の預金や現金は動いていないため、会社での仕訳は不要です。
ただし、領収書や利用明細(支払総額が確認できる書類)を速やかに経理担当者へ提出してもらいます。
この書類が証憑(しょうひょう)となります。
ステップ 2: 会社が経費を認識し、按分額を負債(借入)として計上するとき(重要)
会社が経費として認められる1/3の金額を計算し、「役員に返さなければならないお金」として負債に計上します。
【例1】電気料金の仕訳(毎月)
-
前提: 電気料金の総額が 9,000円 の月。
-
按分額: 9,000円 ×1/3 = 3,000円
|
区分 |
勘定科目 |
借方(左側:費用の発生) |
勘定科目 |
貸方(右側:負債の増加) |
|---|---|---|---|---|
|
経費計上 |
水道光熱費 |
3,000 |
役員借入金 |
3,000 |
|
摘要 |
x月分電気料金 (家事按分 1/3) |
|
|
|
【例2】水道料金の仕訳(2ヶ月ごと)
-
前提: 水道料金の総額が 6,000円 の請求(2ヶ月分)。
-
按分額: 6,000円 ×1/3 = 2,000円
|
区分 |
勘定科目 |
借方(左側:費用の発生) |
勘定科目 |
貸方(右側:負債の増加) |
|---|---|---|---|---|
|
経費計上 |
水道光熱費 |
2,000 |
役員借入金 |
2,000 |
|
摘要 |
X月・Y月分水道料金 (家事按分 1/3) |
|
|
|
⚠️ 総額が3で割り切れない場合の処理
もし総額が10,000円など、3で割り切れない金額だった場合、計算結果は3,333.333…円となります。会計処理では円未満の端数が出るため、以下のように処理します。
-
総額10,000円の場合の按分額: 10,000円 × 1/3 = 3,333・・円
-
処理: 端数は切り捨てて3,333円で仕訳を切るか、継続的に同じ方法(例:四捨五入、切り上げ)で処理します。端数処理の方法は毎年一貫させることが重要です。
|
区分 |
勘定科目 |
借方(左側) |
勘定科目 |
貸方(右側) |
|---|---|---|---|---|
|
経費計上 |
水道光熱費 |
3,333 |
役員借入金 |
3,333 |
|
摘要 |
Z月分電気料金 (10,000円の1/3按分、円未満切捨て) |
|
|
|
ステップ 3: 会社が役員に精算金(立て替え分)を払い戻すとき
ステップ2で「役員借入金」として計上した金額を、会社の現金や預金から役員に支払うことで、負債を解消します。
【例3】精算金の支払い仕訳(現金精算の場合)
-
精算合計額: 3,000円(電気)+ 2,000円(水道)= 5,000円
|
区分 |
勘定科目 |
借方(左側:負債の減少) |
勘定科目 |
貸方(右側:資産の減少) |
|---|---|---|---|---|
|
負債の解消 |
役員借入金 |
5,000 |
現金 |
5,000 |
|
摘要 |
X月光熱費立替金精算(現金払い) |
|
|
|
【例4】精算金の支払い仕訳(銀行振込の場合)
現金ではなく、会社の当座預金口座から振り込んだ場合は、貸方の勘定科目が変わります。
|
区分 |
勘定科目 |
借方(左側:負債の減少) |
勘定科目 |
貸方(右側:資産の減少) |
|---|---|---|---|---|
|
負債の解消 |
役員借入金 |
5,000 |
当座預金 |
5,000 |
|
摘要 |
X月光熱費立替金精算(銀行振込) |
|
|
|
✅ マニュアルチェックリスト:証憑書類と継続性の重要性
-
領収書/明細の保管の徹底:
-
役員から提出された支払い総額がわかる明細(支払日、支払先、総額が記載されたもの)は、必ず7年間(法人の場合)保管してください。
-
この明細は、按分計算の元となる根拠であり、仕訳の正しさを証明する最も重要な書類です。
-
-
按分基準の明確化と文書化:
-
1/3という比率を適用する根拠(例:事務所スペースが全体の1/3であること)を定めた文書(家事按分規定など)を作成し、保管してください。
-
特に使用面積で按分する場合、自宅の間取り図に事業使用部分をマーカーで示し、計算の根拠として添付しておくと完璧です。
-
-
適用の一貫性(継続性の原則):
-
一度1/3と決めたら、毎月(または2ヶ月ごと)の処理でこの比率を継続して適用してください。
-
会計年度の途中で按分比率を安易に変更することは、税務上、恣意的な操作(都合の良い処理)とみなされるリスクがあります。比率を変更する場合は、事務所の拡張など、客観的な事実の変化があった場合に限るべきです。
-
-
未精算残高の確認:
-
経理担当者は、定期的に「役員借入金」の残高を確認してください。この残高が「会社が役員に未だ精算できていない立替金の合計額」となります。
-
精算の遅れは会社の債務(負債)が残ったままになることを意味しますので、速やかな精算(ステップ3の支払い)を心がけましょう。
-
💾 証憑書類の電子保存・スキャナ保存(電帳法対応)
紙で受領した水道料金明細書などを、会社で紙として保管せずにデータとして保存するには、電子帳簿保存法(電帳法)の「スキャナ保存」の要件を満たす必要があります。
1. スキャナ保存の適用
水道料金明細書は、会社が取引相手(水道局など)から受領した証拠書類であり、スキャナ保存の対象となります。
紙の原本をスキャンしてデータ保存すれば、原則として紙の原本の保管は不要となります。
2. 主なスキャナ保存の要件(2022年1月以降)
小規模な会社が満たすべき主要な要件は以下の通りです。
|
要件 |
内容 |
備考 |
|---|---|---|
|
真実性の確保 |
タイムスタンプの付与または履歴管理 |
【緩和された要件】 訂正・削除の履歴が残るシステム(会計ソフトなど)で保存すれば、税務署長への事前承認や定期的な検査は不要になりました。 |
|
可視性の確保 |
検索機能の確保 |
①取引年月日、②取引金額、③取引先の3つの要素で検索できること。Excelファイルなどでの管理でも構いません。 |
|
解像度・色 |
200dpi相当以上の解像度、カラー画像で読み取ること。 |
スマホのカメラや複合機のスキャナでこの要件を満たすか確認してください。 |
|
関連情報の保存 |
入力者情報(スキャン実行者)やスキャン日時を記録すること。 |
記録が残るシステムを使うのが最も簡単です。 |
3. 水道料金明細書のスキャン手順(推奨)
-
紙の受領: 役員から水道料金の紙の明細書を受領します。
-
速やかなスキャン: 明細書の内容を確認し、業務で使用しているスキャナまたはスマートフォンアプリでデータ化(PDFやJPEG)します。電帳法では、受領後概ね7営業日以内の保存が求められます。
-
データ保存と付与: スキャンしたデータ(例:
202409_水道代.pdf)を会計システムにアップロードするか、専用のファイルサーバーに保存し、同時にタイムスタンプを付与(または履歴を記録)します。 -
仕訳との関連付け: ステップ2で作成した仕訳(例2の水道光熱費2,000円)と、このスキャンデータを紐づけて保管します。
✅ マニュアルチェックリスト:証憑書類と継続性の重要性
-
領収書/明細の保管: 役員から提出された支払い総額がわかる明細は、必ず紙または電子データとして7年間(法人の場合)保管してください。
-
按分基準の明確化: 本マニュアル内の「家事按分規定」を印刷・保管し、按分比率の根拠を明確にしてください。
-
適用の一貫性: 一度1/3と決めたら、毎月(または2ヶ月ごと)の処理でこの比率を継続して適用してください。
-
電子保存対応: 紙で受け取る証憑は、「スキャナ保存」の要件(タイムスタンプ、解像度、検索機能)を満たして電子保存し、紙の原本は速やかに破棄して構いません。
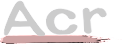



コメント