経理業務お疲れ様です!
法人市民税や法人県民税(これらをまとめて法人住民税と呼びます)の納付書を前にして、「どの勘定科目を使うんだろう?」「なぜ納付時に負債を減らすんだろう?」と疑問に思う経理初心者の方は多いはずです。
この法人住民税は、納付したからといってすぐに経費になるわけではないという特殊性から、会計処理においてつまずきやすいポイントの一つです。
経理初心者の方でもスムーズに業務が進められるよう、会計用語の深い解説から、決算時、そして納付時の正しい仕訳方法、さらには実務で必ず発生する中間申告(予定納税)の処理までを、徹底的に解説します。
1. 知っておきたい!仕訳と税金の基本用語を深掘り
まず、法人住民税の仕訳を完璧にマスターするために欠かせない、基本的な会計用語とその背景を理解しましょう。
① 仕訳(しわけ)とは?:取引を記録する基本ルール
仕訳とは、すべての経済的な取引を「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」という5つの要素に分け、「借方(左側)」と「貸方(右側)」の左右に分けて記録する作業です。
|
側 |
取引の性質 |
意味 |
|---|---|---|
|
借方(左) |
資産の増加、費用の発生、負債の減少 |
会社に何が入ってきたか、何に使ったか |
|
貸方(右) |
資産の減少、収益の発生、負債の増加 |
何がどこから出ていったか、どう儲けたか |
今回の納付処理は、「負債の減少(借方)」と「資産の減少(貸方)」という取引に該当します。
② 法人住民税の二つの顔:「均等割」と「法人税割」
法人住民税は、都道府県や市町村に納める地方税ですが、その性質上、2つの全く異なる部分で構成されています。この違いが、会計処理を複雑にする原因です。
|
構成要素 |
概要 |
会計上の扱い(税務) |
|---|---|---|
|
法人税割 |
会社の利益(所得)に応じて計算される部分。税率は自治体によって異なる。 |
経費にならない(損金不算入):法人税と同じ扱い。 |
|
均等割 |
会社の規模(資本金や従業員数)に応じて定額でかかる部分。赤字でも必ず発生する。 |
経費になる(損金算入):「租税公課」として費用計上。 |
③ 使う勘定科目の役割(重要!)
|
勘定科目 |
会計上の性質 |
意味と役割 |
使用するタイミング |
|---|---|---|---|
|
未払法人税等 |
負債 |
決算で納税額が確定したが、まだ支払期日が来ていない会社が持つ義務(負債)を表す。主に法人税・事業税・住民税の一括処理に使用。 |
主に決算時に計上 |
|
租税公課 |
費用 |
納付した税金や公的な負担金のうち、会社の経費として認められる部分のこと。(例:均等割、印紙税など) |
主に決算時に計上 |
|
普通預金 / 現金 |
資産 |
実際に納付したときに、会社が持つお金が減る(資産の減少)科目。 |
納付時に使用 |
2. 【最も重要】納付時の仕訳は「負債の解消」と心得よ
いよいよ、納付書が届き、実際に銀行で支払った時の仕訳です。
「法人市民税、法人県民税を普通預金から支払いました」という取引は、過去の決算で計上した負債を精算する行為です。
仕訳の考え方(徹底解説)
-
右側(貸方):納付により、会社の普通預金(資産)が減少します。資産の減少は貸方に記入します。
-
左側(借方):決算時に計上した「未払法人税等」(負債)という支払義務が、今回の納付によって消滅します。負債の減少は借方に記入します。
納付時の仕訳例
-
前提: 法人住民税の合計額 250,000円を普通預金口座から支払った。
-
納付時のポイント: 納付時は、法人税割と均等割を分けずに、合計額で、決算時に計上した負債を減らす仕訳を行います。
|
日付 |
勘定科目 |
借方(左) |
勘定科目 |
貸方(右) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
納付日 |
未払法人税等 |
250,000 |
普通預金 |
250,000 |
〇〇期 法人県民税・市民税の納付 |
?? なぜ納付時に「租税公課」を使わないのか?(最重要ポイント) 納付時に「租税公課」を使わないのは、経費になる均等割の金額(費用)は、すでに前の決算日ですでに費用として計上済みだからです。
もし納付時にも「租税公課」を使ってしまうと、同じ金額が費用として二重に計上されてしまい、会社の利益が過小に計上されてしまいます。納付時は、あくまでその計上済みの負債を解消する作業なのです。
3. 【実践編】決算時の仕訳(負債と費用の計上)を理解する
納付時の仕訳を正しく行うためには、その前段階である決算日に、会社がどのような仕訳を行っているかを知っておく必要があります。
決算日には、確定した納税額を「未払法人税等」や「租税公課」として、負債と費用に計上します。
-
前提: 法人住民税の合計 250,000円(内訳:法人税割 180,000円、均等割 70,000円)が確定した。
決算時の仕訳例
|
日付 |
勘定科目 |
借方(左) |
勘定科目 |
貸方(右) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
決算日 |
未払法人税等 |
180,000 |
未払法人税等 |
250,000 |
(1) 法人税割の計上 |
|
決算日 |
租税公課 |
70,000 |
|
|
(2) 均等割の計上 |
|
|
|
|
(対 法人税等) |
|
|
-
(1) 法人税割:会社の利益(所得)にかかる部分は、税務上経費にならない(損金不算入)ため、法人税等調整額の対象となります。借方には「未払法人税等」(法人税等の一部として)を使い、将来支払う負債として貸方に計上します。
-
(2) 均等割:会社の規模にかかる部分は、税務上経費として認められる(損金算入)ため、費用である「租税公課」として借方に計上します。
結果として、貸方(未払法人税等)に負債の合計額 250,000円が計上されます。これが、納付時に消す負債の残高となるわけです。
4. 実務で必須!中間申告(予定納税)の仕訳も押さえよう(応用編)
事業年度が1年を超える法人は、事業年度の途中で「中間申告」として税金の一部を前払いする義務があります。この処理には、もう一つ「仮払金」という勘定科目が登場します。
① 中間申告(予定納税)で納付した時
納付時点では、まだ最終的な納税額が確定していません。そのため、この前払金を「仮払金(仮に支払ったお金)」という資産として計上しておきます。
-
前提: 中間申告で100,000円を普通預金口座から支払った。
|
日付 |
勘定科目 |
借方(左) |
勘定科目 |
貸方(右) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中間納付日 |
仮払金 |
100,000 |
普通預金 |
100,000 |
中間申告による法人税等納付 |
② 決算時に中間納付分を精算する時
期末になり、すべての納税額が確定したら、上記で計上した「仮払金」を、確定した「未払法人税等」(負債の合計)と相殺する仕訳を行います。
-
前提: 期末に確定した納税額が250,000円で、すでに中間申告で100,000円を仮払金として支払っている。
|
日付 |
勘定科目 |
借方(左) |
勘定科目 |
貸方(右) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
決算日 |
未払法人税等 |
180,000 |
仮払金 |
100,000 |
(3) 中間納付額との相殺 |
|
決算日 |
租税公課 |
70,000 |
未払法人税等 |
150,000 |
(4) 差額(未払分)を負債として計上 |
-
(3) 仮払金:中間申告で計上していた資産(仮払金 100,000円)を貸方に計上して消します。
-
(4) 未払法人税等:確定納税額250,000円から、中間納付額100,000円を引いた差額 150,000円が、実際にこれから支払う負債(未払法人税等)として貸方に残ります。
🧐 「税理士いらず」の処理と一般的な仕訳
今回、私の所では「税理士いらず」というソフトを使ってみました。
「税理士いらず」という会計ソフトで自力決算と納税申告書を作成しています。
法人市民税・県民税の支払いと仕訳方法についての仕分けが簡単になっています。
通常は、今まで解説してきたように前の期の期末に未払法人税等で仕分けしたものを、次の期の納税した時に負債を減らす仕分け入力をし、
その期末の決算時に税額が確定したときに未払法人税等の仕分けをしておくとというものです。
しかし、「税理士いらず」の説明では次のようになっていて、上記の仕分け操作としなくていいということです。
「税理士いらず」は、簡便な操作で決算書を確定させるために、期末処理である申告調整処理で、当期の法人税等の計上処理と一緒に、当期中に納付した前期分の税金の納付仕訳や、当期の中間納付仕訳を作成しています。
したがって、決算調整処理を完了させて確定決算書を作成すれば、決算書では現金残高などの整合性が取れます。
なお、環境設定メニューのその他の設定タブで、納付仕訳の作成可否および、相手科目を指定することもできます。
「税理士いらず」での処理
「税理士いらず」の機能は、決算書を確定させるための「申告調整処理」の中で、以下の3つの処理を自動で行っていると解釈できます。
-
当期法人税等の計上処理:期末に当期分の税額(この場合は均等割)を「未払法人税等」として計上する仕訳。
-
前期分の税金の納付仕訳:当期に納付した前期分の税金について、負債科目(未払法人税等)を減らす仕訳。
-
当期の中間納付仕訳:もし中間納付があれば、それを「仮払法人税等」として処理する仕訳と、期末に「未払法人税等」と相殺する仕訳。
⚠️ 結論
ユーザーが通常手動で行う「納税時の負債(未払法人税等)を減らす仕訳」 や 「期末の税額計上仕訳」 は、「税理士いらず」が決算調整処理の一環として自動で作成し、整合性を取ってくれるため、手動で改めて入力する必要はない、ということです。
一般的な会計での仕訳(均等割りのみの場合)
一般的な会計ソフトでの仕訳の流れは、以下の通りです。
| 時期 | 内容 | 借方(費用/資産の増加・負債の減少) | 貸方(収益/資産の減少・負債の増加) |
| 前期末 | 当期税額(均等割)の確定・計上 | 法人税、住民税及び事業税(費用) | 未払法人税等(負債) |
| 当期中 | 前期税額の納付 | 未払法人税等(負債の減少) | 現金または預金(資産の減少) |
| 当期末 | 当期税額(均等割)の確定・計上 | 法人税、住民税及び事業税(費用) | 未払法人税等(負債) |
「税理士いらず」は、このうち太字の部分を含む一連の処理を、決算処理の機能に組み込んでいるため、
ユーザーは日々の取引入力や通帳の出金処理として入力する代わりに、ソフトの決算機能に任せてしまって良い、という仕組みです。
💡 利益が出た場合の会計処理のポイント
利益が出て法人税割が発生した際の、一般的な会計上の流れと「税理士いらず」での処理の関係は以下の通りです。
1. 納付税額の確定
期末の決算処理により、以下の税額が確定します。
-
法人税(国税)
-
地方法人税(国税)
-
法人住民税(県民税・市民税)
-
均等割
-
法人税割(利益が出たため発生)
-
-
法人事業税・特別法人事業税(地方法人税、利益が出たため所得割などが発生)
2. 一般的な会計での期末仕訳(手動の場合)
これら確定した全ての税額を合計し、すでに支払っている中間納付額(仮払法人税等) を差し引いた残りが、未払法人税等として計上されます。
| 借方 | 貸方 |
| 法人税、住民税及び事業税 (費用) | 仮払法人税等 (資産の減少: 中間納付分を相殺) |
| 未払法人税等 (負債: 納税額の残高) |
3. 「税理士いらず」での処理
「税理士いらず」の「申告調整処理」は、この上記の期末仕訳を自動で作成し、さらに期中にあった前期分の納税時の仕訳も自動で処理します。
そのため、ユーザーは、
-
期中:中間納付があった場合、通常は「仮払法人税等」として手動で仕訳入力が必要です。ただし、ソフトの設定によってはこれも自動で作成されることがあります。
-
期末:決算が確定し、税額が算出されたら、「申告調整処理」を実行するだけで、上記の未払法人税等の計上と仮払法人税等の精算が自動で行われます。
ポイント:
利益が出た場合の処理で複雑になるのは中間納付の有無ですが、納付時の仕訳を「仮払法人税等」として正しく入力しておけば、「税理士いらず」が期末に自動で精算してくれる仕組みです。
🔎 中間納付があった場合の確認
もし当期中に中間納付(予定納税)を行っている場合は、その納付時の仕訳がソフトにどのように入力されているかを確認するとより安心です。
1. 納付時の一般的な仕訳
| 借方 | 貸方 |
| 仮払法人税等 (資産) | 現金または預金 (資産の減少) |
2. 「税理士いらず」での自動精算
この「仮払法人税等」の残高は、期末の「申告調整処理」で確定税額と相殺され、残額(未払法人税等)が負債として計上される、という流れです。
もし「税理士いらず」の操作で中間納付の入力が必要な手順があれば、そこだけはマニュアルに従って行う必要があります。
まとめ・仕訳の鉄則と次のステップ
法人住民税の仕訳は、「均等割が経費になる」という特殊性からやや複雑ですが、流れを整理すれば簡単です。
|
タイミング |
目的 |
使う勘定科目(借方) |
使う勘定科目(貸方) |
鉄則 |
|---|---|---|---|---|
|
決算日 |
納税額を確定し、負債・費用を計上する。 |
均等割:租税公課 法人税割:未払法人税等 |
未払法人税等 |
負債(支払義務)を計上する |
|
納付日 |
決算で計上した負債を解消し、現金を減らす。 |
未払法人税等 |
普通預金/現金 |
負債の解消が目的 |
|
中間納付時 |
将来の納税額を前払いする。 |
仮払金 |
普通預金/現金 |
資産(前払金)を計上する |
法人住民税の納付は、「負債の解消」として処理する!この鉄則と、中間申告の「仮払金」処理をセットで覚えておけば、経理処理は万全です。
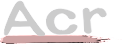



コメント