経理初心者の方が必ず一度は出会う「預金利息の仕訳」。
法人名義の貯金通帳に少しだけ利息が振り込まれているのを見つけても、「なんだか税金が引かれているけど、どう仕訳したらいいの?」と戸惑ってしまうかもしれません。
利息の金額は小さくても、この仕訳を正しく行うことは、会社の税金を正確に計算する上で非常に重要です。
この記事では、普通預金に利息が支払われた時の会計処理を、初心者の方にも分かりやすいように基本用語の解説からステップ形式で徹底的に解説します。
Step 1: まずは基本用語をチェック!仕訳のルールを徹底理解
仕訳の解説に入る前に、経理で最も重要な概念である「勘定科目」「借方」「貸方」について、その意味と役割を深く理解しておきましょう。
|
用語 |
読み方 |
意味 |
|---|---|---|
|
仕訳 |
しわけ |
すべての経済的な取引を、ルールに従って「勘定科目」を使って「借方」と「貸方」に分けて記録すること。複式簿記の基本です。 |
|
勘定科目 |
かんじょうかもく |
取引の内容を分かりやすく分類するための名前(例:現金、売上、給料など)。この科目を使い、会社の財産の状態(資産、負債、純資産)や経営成績(収益、費用)を示します。 |
|
借方 |
かりかた |
仕訳の左側。「資産の増加」「負債の減少」「費用の発生」を記録する場所。 |
|
貸方 |
かしかた |
仕訳の右側。「資産の減少」「負債の増加」「収益の発生」を記録する場所。 |
|
普通預金 |
ふつうよきん |
銀行の普通預金口座。会社にとって財産なので資産を表す勘定科目。 |
|
受取利息 |
うけとりりそく |
会社が銀行などから受け取った利息のこと。会社にお金を増やす効果があるため収益を表す勘定科目。 |
|
法人税等 |
ほうじんぜいとう |
法人が支払うべき税金(法人税、住民税、事業税など)の総称。利息の源泉徴収に使われる科目は、実務上「法人税等」または「仮払法人税等」のいずれかを使用します。 |
★利息の仕訳の肝は「3つの金額」
銀行から利息が振り込まれる場合、通帳に記載されている金額は、利息の全額ではなく、税金が差し引かれた後の金額です。
この取引を完全に記録するためには、「利息の全額」「引かれた税金」「手元に入ったお金」の3つの金額を分けて記録する必要があります。
|
金額 |
意味 |
勘定科目(後述) |
仕訳の方向 |
|---|---|---|---|
|
利息総額 |
会社が本来もらうべき利息の全額。 |
受取利息 (収益) |
貸方(収益の発生) |
|
源泉徴収税額 |
利息から先に差し引かれた税金。 |
法人税等 (資産) |
借方(資産の増加) |
|
差引入金額 |
通帳に実際に入金された金額。 |
普通預金 (資産) |
借方(資産の増加) |
つまり、借方(2つの金額)と貸方(1つの金額)が一致することで、取引の全体像を記録するのです。
Step 2: なぜ税金が引かれているの?(源泉徴収の仕組み)
通帳を見ていただくと、「利息」として計上された金額から、「源泉所得税」や「源泉地方税」といった名目で税金が差し引かれていることが分かります。
1.銀行が行う「源泉徴収」の正体
これは、会社が利息を受け取る際に、銀行が会社に代わってあらかじめ税金を差し引いて国や地方自治体に納める仕組みがあるためです。これを源泉徴収と呼びます。
法人が受け取る利息の源泉徴収税率は、原則として20.315%(所得税及び復興特別所得税 15.315% + 地方税 5%)が適用されます。
2.源泉徴収税額が「資産」になる理由
源泉徴収された税金(法人税等)は、会社が最終的に納めるべき法人税等の総額の一部を、期中に「前払い」したものとして扱われます。
-
税金を納める時: 会社は費用(法人税等)を認識します。
-
利息の源泉徴収時: まだ会社の利益が確定していない段階で、先に税金が徴収されています。
そのため、この源泉徴収税額は、仕訳上は「後で精算されるべき前払い金」という資産として処理されます。確定申告の際に、この前払いした金額を、最終的な納税額から差し引いて精算することになります。
<確定申告時の精算イメージ> 最終的な法人税額が10万円だったとします。 すでに利息で源泉徴収された金額(法人税等)が2千円あった場合、実際に納める残りの税金は「10万円 - 2千円 = 9万8千円」となるわけです。
Step 3: 具体的な仕訳の考え方と手順
ここでは、以下の具体的な数字を例に、借方・貸方のルールに基づいて仕訳を組み立ててみましょう。
|
取引内容 |
金額 |
|---|---|
|
利息総額(本来の収益) |
1,000円 |
|
源泉徴収税額(差し引かれた税金 20.315%相当) |
203円 |
|
差引入金額(通帳に入った実際の金額) |
797円 |
1. 収益の発生を記録する(貸方:右側)
会社は利息という「収益」(売上などと同じ、お金を増やす元)を得ました。収益の発生は、ルール通り貸方(右側)に記録します。
|
勘定科目 |
貸方 (Credit) |
理由 |
|---|---|---|
|
受取利息 |
1,000 |
収益の発生 |
2. 資産の増加を記録する(借方:左側)
利息の一部が「普通預金」という形で会社に入り、「資産」が増えました。資産の増加は借方(左側)に記録します。
|
勘定科目 |
借方 (Debit) |
理由 |
|---|---|---|
|
普通預金 |
797 |
資産の増加(実際に入金された金額) |
3. 前払いした税金を記録する(借方:左側)
差し引かれた203円は、後で返ってくるか、納税額から差し引かれる「前払いした税金」です。これも資産の扱いとなり、資産の増加として借方(左側)に記録します。
|
勘定科目 |
借方 (Debit) |
理由 |
|---|---|---|
|
法人税等 |
203 |
資産の増加(前払いした税金) |
Step 4: 仕訳の完成形と追加例
Step 3の要素をすべてまとめると、仕訳は以下のようになり、借方(797 + 203 = 1,000円)と貸方(1,000円)の金額が必ず一致します。
|
日付 |
勘定科目 |
借方 (Debit) |
勘定科目 |
貸方 (Credit) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
xx/xx |
普通預金 |
797 |
受取利息 |
1,000 |
xx銀行利息入金 |
|
|
法人税等 |
203 |
|
|
源泉徴収税額(20.315%) |
★ポイント再確認
|
借方(左側)のポイント |
貸方(右側)のポイント |
|---|---|
|
実際に通帳に入った金額を普通預金で記録する(資産の増加)。 |
本来の利息総額を受取利息で記録する(収益の発生)。 |
|
差し引かれた税額を法人税等で記録する(前払い資産の増加)。 |
|
追加例:利息総額が5,000円の場合
利息総額 5,000円、源泉徴収税額 1,016円(5,000円 × 20.315%)、差引入金額 3,984円の場合の仕訳はこうなります。
|
日付 |
勘定科目 |
借方 (Debit) |
勘定科目 |
貸方 (Credit) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
xx/xx |
普通預金 |
3,984 |
受取利息 |
5,000 |
xx銀行利息入金 |
|
|
法人税等 |
1,016 |
|
|
源泉徴収税額 |
Step 5: 極めて少額で内訳が不明な場合の対処法
小さな会社で起こりがちなケースとして、通帳に数円〜十数円程度の利息が入金されたものの、銀行からの通知がなく、源泉徴収税額(引かれた税金)がいくらだったのか、通帳を見ても正確に分からないという状況があります。
この場合でも、仕訳の原則は変わりませんが、実務上の対応方法が2つあります。
対処法1:法定税率で「逆算」して正確な仕訳を行う(推奨)
税金の内訳が不明でも、法人の利息の源泉徴収税率は「20.315%」で固定されています。
この税率を使って、通帳に入金された金額から本来の利息総額を逆算し、仕訳を組み立てるのが最も正確です。
<例:通帳に3円入金されていた場合>
-
差引入金額(手取り):3円(普通預金 ← 借方)
-
手取りの割合:100% – 20.315% = 79.685%
-
利息総額(本来の収益):3円 ÷ 0.79685 ⇒ 3.765円
ここでは、会計上の重要性(金額の重要性)を考慮し、円単位に丸めて処理します。(※千円単位の仕訳が多い場合は、円単位まで正確に記録することを推奨します。)
-
利息総額(受取利息): 4円
-
源泉徴収税額(法人税等): 4 – 3 = 1円
|
日付 |
勘定科目 |
借方 (Debit) |
勘定科目 |
貸方 (Credit) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
xx/xx |
普通預金 |
3 |
受取利息 |
4 |
通帳入金利息(逆算値) |
|
|
法人税等 |
1 |
|
|
源泉徴収税額(逆算値) |
対処法2:重要性が低いとして簡便処理を行う(非推奨だが現場で発生)
利息の金額が極めて少額(数円程度)で、決算に与える影響がほとんどないと判断できる場合、手間を省くために、入金された金額をそのまま利息の総額として処理してしまうケースが実務上あります。
この方法では、本来「資産」として計上すべき源泉徴収税額を無視することになるため、税務上は厳密ではありませんが、金額の重要性が低い場合に限定して適用されることがあります。
-
この処理を行うと、法人税の確定申告の際、前払い税金(法人税等)として精算できる金額が計上されないことになります。つまり、税金を払いすぎている状態になります。
<例:通帳に3円入金されていた場合(簡便処理)>
|
日付 |
勘定科目 |
借方 (Debit) |
勘定科目 |
貸方 (Credit) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
xx/xx |
普通預金 |
3 |
受取利息 |
3 |
通帳入金利息(簡便処理) |
【結論】 基本的には、対処法1(逆算処理)で正確に仕訳を切ることをおすすめします。
数円であっても、前払いした税金(法人税等)を資産として正しく計上しておかないと、その分を税務署に請求できなくなってしまうからです。
この仕訳を覚えておけば、今後利息が入金されるたびにスムーズに処理できます。
小さな取引ですが、ひとつひとつ正しく記録して、正確な会計を目指しましょう!
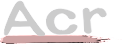



コメント