小規模な会社や設立したばかりの会社では、コスト削減のため役員のご自宅の一部を事務所として使用することがよくあります。
この「自宅事務所」の形態をとる場合、自宅にかかる費用の一部を会社の経費(損金)として計上できます。
特に質問が多い固定資産税をはじめとする不動産関連費用の経費計上(家事按分)の考え方と、税務調査で否認されないための明確なルール設定と文書化の重要性について詳細に解説します。
1. 固定資産税の経費計上の基本原則と法的根拠
固定資産税は、不動産(土地や建物)を所有していること自体に課税される地方税です。
自宅を事務所として使っている場合、その費用を「個人」の家事費と「法人」の事業費に合理的に分ける処理を家事按分(かじあんぶん)と呼びます。
経費にできるのは「事業に使用している割合」のみ
役員個人が納税した固定資産税のうち、会社の事業遂行のために使用している合理的な割合に相当する金額だけを、会社の経費(勘定科目:租税公課)として計上し、役員へ精算することが可能です。
家事関連費の損金算入の条件
法人税法上、家事関連費(事業とプライベートの両方に関わる費用)を損金(経費)として認めてもらうためには、「業務の遂行上必要であること」、そして「その必要である部分を明確に区分できること」が必須条件となります。
この「明確な区分」を客観的に示すための作業こそが、合理的な按分であり、それを裏付ける文書化なのです。
役員報酬との区別(重要なポイント)
按分によって役員へ精算される金額は、役員への「給与」や「報酬」ではありません。
これは、「会社が使うべき費用を役員が一時的に立て替えてくれたもの」を会社が返済するという位置づけです。
そのため、事前に按分ルールを定めておくことで、税務上、役員への利益供与(給与課税)と見なされるリスクを回避できます。
2. 合理的な按分基準の設定と費用の関連性
按分率の設定に明確な法律上の規定はありませんが、「事業の実態に即している」ことが重要です。
費用にはそれぞれ性質があり、その性質に応じて最も合理的な基準を選択する必要があります。
不動産関連費用「床面積基準」が必須
固定資産税や建物の減価償却費、火災保険料といった費用は、その不動産が存在し、物理的に占有していることによって発生する費用です。
これらは時間の経過や使用量に比例する費用ではありません。
|
基準 |
適用費用 |
固定資産税への適用理由 |
|---|---|---|
|
床面積基準 |
固定資産税、減価償却費、火災保険料、賃料(家賃) |
最も推奨。 建物全体の床面積のうち、事務所として専属的・継続的に使用している部分の面積割合で按分します。不動産を基盤とする費用であるため、物理的な占有割合が最も合理性が高いとされます。 |
|
時間基準 |
水道光熱費、通信費(電話代、ネット代の一部) |
非推奨(補助的に使用)。費用が発生するタイミングが使用時間に直結するため、これらの按分に用いるのが一般的です。 |
【按分率の計算例の具体化】
自宅の3分の1の面積を事務所として使用している場合を例とします。
-
自宅の総床面積: 100
-
事務所として使用する面積(仕事専用部屋):33.3
-
事業使用割合: 33.3×100=33.3%=3分の1
→ この 33.3%を固定資産税の総額に乗じた金額が、会社の経費として精算できる金額となります。
ポイント: 賃貸物件の家賃按分の場合も、同様に床面積基準が基本となります。
3. 会計処理の仕訳例とタイミング
固定資産税は年に一度、または数期に分けて役員個人に納付書が届き、納付されます。
1. 役員が固定資産税を納付した際(個人の処理)
会社は、役員が納付したことの証拠として、納税通知書(明細)と領収書または支払い証明のコピーを必ず保管します。
2. 会社が按分相当額を役員に精算する際
例として、役員が固定資産税300,000円を全額支払い、事業使用割合が 30%=100,000円の場合。
会社から役員へ100,000円を振り込む場合:
|
借方勘定科目 |
借方金額 |
貸方勘定科目 |
貸方金額 |
|---|---|---|---|
|
租税公課 |
100,000 |
現金または普通預金 |
100,000 |
|
摘要 |
役員〇〇 固定資産税家事按分30%精算 |
|
|
※資金繰りが間に合わない場合: すぐに精算せず、会社が役員から一時的にお金を借りている形とする場合は、貸方に「役員借入金」を使用します。
この場合、将来的に役員へ返済することになります。
|
借方勘定科目 |
借方金額 |
貸方勘定科目 |
貸方金額 |
|---|---|---|---|
|
租税公課 |
100,000 |
役員借入金 |
100,000 |
|
摘要 |
役員〇〇 固定資産税家事按分30% |
|
|
4. 税務リスクを避けるための「文書化」と税務上の注意点
按分は、税務調査で最も厳しくチェックされる項目の一つです。
経費計上した金額の合理性を明確に証明するため、必ず社内規定や費用負担に関する覚書を作成し、会社と役員間で合意を得ておく必要があります。
【税務上の重要チェックポイント】
A. 不明確な精算による「みなし贈与」リスク
会社が役員へ精算する金額が、事前に定めた合理的な按分ルールを超えて過剰な場合、その超過分は役員への給与(賞与)と見なされ、源泉徴収漏れを指摘される可能性があります。
逆に、本来精算すべき金額よりも極端に低い場合、役員が会社に無償で不動産を提供している(賃貸料を放棄している)と見なされ、みなし贈与などの問題が生じる可能性もゼロではありません。
B. 個人の確定申告における「50%ルール」(参考情報)
本記事は法人税を前提としていますが、個人事業主の場合(白色申告者)は、家事関連費の事業使用割合が50\%を超えなければ原則として経費計上が認められません。
法人の場合はこのような厳格な50%基準はありませんが、事業使用割合が 50% を超える場合には、税務署は特にその合理性について慎重に判断します。
【文書に含めるべき重要事項】
文書化の際に最も重要なのは、「なぜこの割合なのか」を客観的に説明できることです。
|
項目 |
記載すべき内容 |
根拠資料として保管すべきもの |
|---|---|---|
|
使用場所 |
どの物件のどの部分(何階のどの部屋など)を事務所として使用しているか。 |
登記事項証明書、建物の図面(間取り図) |
|
按分基準 |
事業使用割合(例:3分の1)を決定した根拠。 (例:総床面積100に対し、事務所専用利用の部屋が33.3平方mであるため。) |
建築図面、または自社作成の面積算定表 |
|
費用負担の範囲 |
会社が按分で負担する費用の種類。 (例:固定資産税、減価償却費、火災保険料など) |
納税通知書、保険証券 |
|
精算方法 |
会社から役員へいつ、どのように精算するか(年度ごと、月ごとなど)。 |
– |
【付録】役員社宅(自宅事務所)に関する費用負担覚書(例文)
下記例文は、役員個人が所有する自宅の一部を会社事務所として使用し、その費用を按分するための取り決めを明確にするものです。
役員社宅(自宅事務所)に関する費用負担覚書
〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と役員 氏名(以下、「乙」という。)は、乙所有の不動産を甲の事務所として使用するにあたり、以下の通り覚書を締結する。
第1条(使用目的)
乙は、乙所有の下記物件の一部を、甲の事業を遂行するための主たる事務所(以下、「自宅事務所」という。)として甲に使用させるものとする。
|
所在地 |
建物構造 |
建築年月日 |
役員氏名 |
|---|---|---|---|
|
〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 |
木造2階建て |
平成〇年〇月〇日 |
(乙の氏名) |
第2条(事業使用割合)
自宅事務所の総床面積〇〇平方mのうち、甲の事業専用に使用するスペースの面積は、総面積の3分の1とし、この割合を甲の事業使用割合とする。
(※注:この割合の算定根拠となる間取り図、各部屋の面積、及び按分計算表は、本覚書に添付し、税務調査に備えるものとする。)
第3条(甲が負担する費用)
甲は、自宅事務所の維持・管理に要する費用(以下、「関連費用」という。)のうち、前条で定めた事業使用割合(3分の1)に相当する金額を、事業に必要な経費として乙に負担(精算)するものとする。
2.甲が負担する関連費用は、次の各号に定めるものとする。なお、費用によって時間基準を適用する際は、その計算根拠(業務時間)を明確に記録する。
-
固定資産税(都市計画税を含む):面積基準3分の1
-
建物の減価償却費(建物のみ。土地は対象外):面積基準3分の1
-
火災保険料・地震保険料(建物部分のみ):面積基準3分の1
-
水道光熱費(電気代、ガス代、水道代):使用実態に基づき、在宅時間のうちの業務時間割合で按分する。
-
通信費(インターネット回線利用料等):使用実態に基づき、使用時間または使用日数で按分する。
-
修繕費(自宅事務所として使用する部分の修繕に要する費用):実費精算。
第4条(精算方法)
甲は、乙が関連費用を支払い後、乙からの請求(領収書または納税通知書を添付)に基づき、原則として関連費用が確定した事業年度内に、前条第1項の事業使用割合に相当する金額を乙に対し支払う(精算する)ものとする。
第5条(覚書の有効期間)
本覚書は、〇年〇月〇日から有効とする。事業使用割合に大きな変更が生じた場合、甲乙協議の上、覚書を改定するものとする。
第6条(その他)
本覚書に定めのない事項については、甲乙協議の上、円満に解決を図るものとする。
|
〇年〇月〇日 |
|
|---|---|
|
甲:〇〇株式会社 |
乙:役員 氏名 |
|
所在地:(会社の住所) |
住所:(役員の住所) |
|
代表者氏名:(代表者署名・捺印) |
氏名:(役員署名・捺印) |
このマニュアルは、役員宅の固定資産税を適正に経費計上し、税務上の健全性を保つために不可欠なルールです。
運用開始前に、必ず本規定の内容を確認し、役員と会社との間で認識の統一を図ってください。
【付録簡略版】固定資産税等按分に関する合意書(役員宅事務所利用)例文
〇〇株式会社(以下、「甲」)と役員 氏名(以下、「乙」)は、乙所有の不動産を甲の事務所として使用することに伴う費用負担について、以下の通り合意する。
1. 対象物件と使用目的
乙が所有する下記物件の一部を、甲の主たる事業活動のための事務所として使用する。
|
所在地 |
建物構造 |
役員氏名 |
|---|---|---|
|
〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 |
木造2階建て |
(乙の氏名) |
2. 事業使用割合(按分基準)
上記物件の総床面積のうち、甲の事業専用スペースとして利用する面積は、総面積の3分の1とし、この割合を事業使用割合とする。
(※注:本割合の算定根拠となる間取り図、面積計算表を添付し、保管する。)
3. 甲が負担する費用と精算
甲は、下記の不動産関連費用について、前項で定めた事業使用割合3分の1に相当する金額を、事業経費として乙へ精算する。
|
費用項目 |
按分基準 |
会社の負担割合 |
|---|---|---|
|
固定資産税(都市計画税含む) |
面積基準 |
3分の1 |
|
建物の減価償却費(建物部分のみ) |
面積基準 |
3分の1 |
|
火災保険料、地震保険料(建物部分のみ) |
面積基準 |
3分の1 |
4. 精算方法
乙が費用を支払い後、納税通知書等の証拠書類を甲へ提出し、甲は速やかに合意した事業使用割合に基づき算定した金額を乙へ支払う(精算する)。
|
〇年〇月〇日 |
|
|---|---|
|
甲:〇〇株式会社 |
乙:役員 氏名 |
|
所在地:(会社の住所) |
住所:(役員の住所) |
|
代表者氏名:(代表者名) |
氏名:(役員名) |
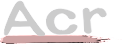



コメント